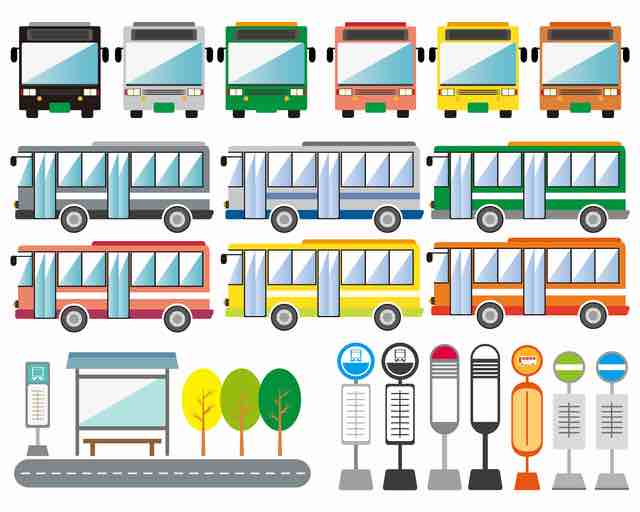
<毎月第1月曜日更新(祝日の場合は翌営業日更新)>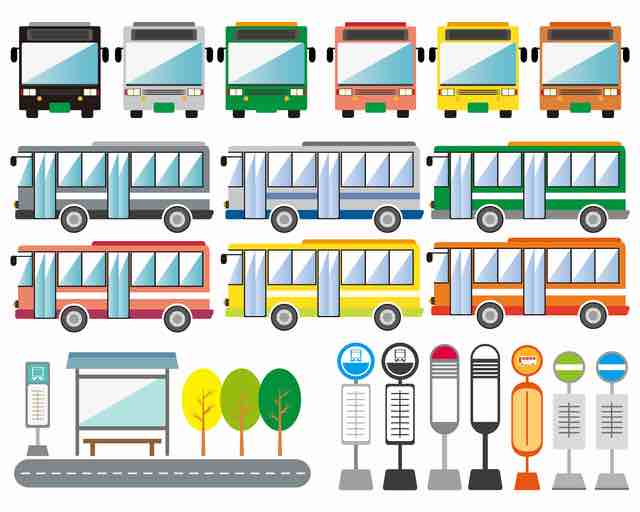
1995年に、東京都武蔵野市でコミュニティバス(ムーバス)が誕生してから、全国の地方自治体が武蔵野市を視察するようになる。そして、政策的コピーを行う地方自治体が増え、全国にコミュニティバスが誕生する。2000年前後には、全国のかなりの自治体で地域交通の重要手段としてコミュニティバスが席巻する。もっとも武蔵野市は、高齢者の歩行特性や生活特性等をしっかり調べ、マーケティングサーベイの効果があり、今日まで堅実な維持が出来ている。まさしく最近の言葉でいえば、データドリブンデザインなコミュニティバスの成功事例となった。生活者のアクティビティ分析や心理分析、都市・地域特性をしっかりと行えば、コミュニティバスが成功することを証明した部分がある。一方で、雨後の筍状態となるからには、そうした事前調査及び計画がおざなりにされ、生活者に見放されるコミュニティバスも増えた訳である。そしてコミュニティバスそのものは、武蔵野市のような狭隘路周辺での移動支援手段だけでなく、路線バス廃止代替の単なる地方自治体運営による移動手段になる場合も増えていった。無計画→乗客減少→本数減少→運行取りやめの流れとなるコミュニティバスも平成中頃には増えていった。やむなくコミュニティバスが、地域内での買物支援・通院支援・役所周りの支援に使われるようになり、色々な地点を結ぶことで路線長が長くなる事例も増えた。そして使い勝手が悪くなり悪化の一途を辿る事例も増加した。
一般の路線バス事業については、事業の参入が路線ごとの免許制であったところ、事業者ごとの許可制へ移行した。2002年2月のいわゆる「バス事業の規制緩和」である。1985年以降、路線バス事業の経営悪化がモータリゼーション進展で目立つようになった。1985年頃から2000年頃の平成初期は、歴史のある地域の路線バス事業者だけに任せてはおけないのではないか、路線バス事業に参入したい新参事業者にも門戸を開いた方が地域のモビリティ維持に良いのではないか、という政策議論もなされるようになった。そこで「改正道路運送法」施行にシフトし2002年2月以降は乗合バス事業の公的規制が実質的に取り払われ新規参入のハードルが下がることになった。これは非常に大きなターニングポイントとなり規制緩和で乗合バス事業への参入が容易となり、新規バス事業を行いたいタクシー事業者、宅配事業者等には可能性が拡がり朗報になった。貸切バス専業事業者及びタクシー事業者、トラック運送会社は、路線バス事業展開を狙ってきた事業者もありこれは概ね歓迎された。
一方、既存の路線バス事業者にとっては、赤字路線からの撤退が事前届出制へ緩和される形となった。最近では、月ごとや年ごとに1本というような形で存在する免許維持路線も減り、コスト削減は行いやすくなった。その代替にコミュニティバスが活用されるようにもなった。地域の路線バスやコミュニティバスの維持については、地域公共交通活性化協議会を各地方自治体が設置し、財政措置等を含めて各地方自治体での主体的議論に委ねられるようにシフトした。この規制緩和を受け、既存の乗合バス事業者では不採算路線の統廃合や減便が進んだが、地域から移動手段が消える場所も増えて色々な悪い影響も出始めている。
路線バスでも、公営バスでは長引く不況と地方自治体の財政悪化、公務員スタッフ雇用による給与額高騰等で、民間委託や民営化等もやむなく議論されるようになった。2002年の大阪市交通局による大阪運輸振興への委託開始(2018年に大阪市交通局が大阪シティバスに民営化)、2003年の東京都交通局による都営バスの一部営業所のはとバス委託開始、2007年の横浜市交通局による横浜交通開発への委託開始等が代表的である。京都市交通局では、同一営業所に複数委託事業者が参入する事例も生じ、制服は京都市交通局のものであってもそれを着る人間は色々な会社のスタッフ、という状況で経営悪化を象徴する状況となった。
高速バスについては、寝台列車の車輛老朽化による撤退、不景気による安価な移動手段に対する期待などで、長距離夜行を中心に高速バス=バス業界での救世主という捉えられ方が平成初期には主流になる。西日本鉄道の「はかた号」(東京-福岡)のような長大老舗路線も生まれ、若者や出張者も利用するようになった。一方で2017年には東京-大阪や東京- 広島線に「完全個室型」のバスであるドリームスリーパーが、関東バスや中国バス等の手で運行されるようになる。3列で30人弱が座れる高速夜行バスが主流となり、その後は若者向けの4列車輛使用、個室で10名程度収容の車輛等、ニーズに応じて高速バス車輛を使い分けられる環境にシフトしていった。こうした中で、2000年代初頭には都市間高速ツアーバスが急増し、価格競争が激化してしまった。ツアーバスは、高速バスに見立てて、ツアー形式で集客し運行するものであったが、サービスの質の低下やコストダウンのために運転士が低賃金で過労となり、度重なるツアーバスの死傷事故が起きた。このため、国土交通省自動車局は2012年7月30日に「新高速乗合バス」制度を定めている。省令や通達の改正を行い、同日時点でツアーバスは新高速乗合バスへ一本化されることにシフトしていった。
このように平成時代は、路線バス・高速バス共々大きな変化が生じた。路線バスは乗客が減少の一途を辿り、廃止やコミュニティバスへのシフトが進んだ。高速バスは儲かる手段となったが、新規事業者も増えて伝統的な事業者との競争が激化し寡頭競争状況に突入した。

図2-16 関東バスのドリームスリーパーの車内。完全個室式で人気が高い。

図2-17 全但バスの城崎温泉-大阪の高速バス。昼に走るバスだが車内後部は個室がある。

図2-18 長さで有名な西日本鉄道の夜行高速バス「はかた号」
Copyright © Nu-su Publishing Inc. All Rights Reserved.